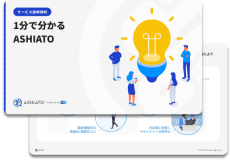ハロー効果とは
ハロー効果(halo effect)とは、社会心理学の用語で、「ある対象を評価する際に、それが持つ目立つ特徴に引きずられ、他の特徴や対象全体の評価まで歪められる心理現象(認知バイアス)」のことを指します。
ある対象を評価するときに、「一部の特徴的な印象に引きずられて全体の評価をしてしまうこと」と解釈できます。例えば、「見た目が整っていると仕事ができそう」「大人気アイドルをCM起用すると売れる」などのイメージも、ハロー効果に当たります。
心理学者のエドワード・ソーンダイクが1920年の論文で紹介した比較的古い概念ですが、戦略人事や人事領域のデータ化など、近年の人事領域の進化の中で改めて注目度が高まっています。
ハロー効果は、「hello」ではなく「halo」効果
ハロー効果の「ハロー」は、英語の挨拶の「hello」ではなく、「halo」という綴りの英単語が使われています。haloとは「後光」や「光輪」を意味し、これは西洋の宗教画などで聖人の頭上に描かれる光の輪を指します。ここから、ハロー効果は「後光効果」「光背効果」と呼ばれる場合もあります。後光が差すような強い特徴が、評価者の認知を歪ませる、という意味ですね。このような心理的な現象は洋の東西を問わず語られており、日本のことわざ、「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」「あばたもえくぼ」なども同じ効果を表しています。 ハロー効果の身近な例
ハロー効果の身近な例として、恋愛でのハロー効果として先述の「あばたもえくぼ」を例に確認して見ましょう。
好意を抱く相手は、「あばたもえくぼ」というように、短所も長所に見えてしまうことがあります。
「あばたもえくぼ」は、好意を持った相手には、醜い「あばた」も、可愛らしい「えくぼ」のように見えるということから、「好きな相手は欠点すら長所にみえる」ということを指すことわざです。
このことわざ「あばたもえくぼ」は、好意的な印象に引きずられて、全体の評価をしてしまうハロー効果を表しています。
ハロー効果の人��事領域での例
人事評価では、ある一部の評価が高いと、それに引きずられ「全体を高い評価」に、ある一部の評価が低いと、「全体を低い評価」にする傾向がハロー効果として現れます。
採用面接では同じ受け答えであっても、出身校や履歴書の内容に引きずられ、評価にバイアスがかかってしまうこともハロー効果の現象です。面接は第一印象が大きく左右されますが、これもハロー効果であり、採用を担当する面接官は予め印象に左右されないようにハロー効果を認識しておく必要があるでしょう。
ハロー効果の2つの種類
ハロー効果は、「ポジティブ・ハロー効果」と「ネガティブ・ハロー効果」の2つに分かれます。以下でそれぞれの違いを見ていきましょう。
ポジティブ・ハロー効果とは
ポジティブ・ハロー効果は、評価者がある人物を評価するときに、特定の項目の評価が高いと感じた場合に、別の項目も同じく高評価を下す現象を指します。
例えば、ノーベル賞を受賞した科学者が、専門外の経済について解説したとしましょう。この時、いくらその科学者が経済については門外漢だとわかっていても、ついつい「頭の良い人物が言っているなら正しいだろう」とポジティブな評価を下してしまうことがあるでしょう。このような認知の“クセ”がまさにポジティブ・ハロー効果と言えます。
��ネガティブ・ハロー効果とは
ポジティブ・ハロー効果の逆が、ネガティブ・ハロー効果です。評価者が、人物の悪い特徴をその人の全体評価に結びつけてしまい、他の良い特徴を見逃し、実際の実力より低い評価を下してしまうことです。
例えば、近年のアメリカ社会で顕著な、肥満を自己管理能力の欠如と結びつける考え方がこれに該当します。生理的な要素が強い体型や体重という1事象を、その人物の仕事や社会活動における「だらしなさ」に直結させる考え方に、多くの場合論理的な根拠はありません。しかし、このようなバイアスは人材評価において当たり前のように存在しているのが実際です。
ハロー効果とピグマリオン効果の違い
ハロー効果と似た概念にピグマリオン効果(pygmalion effect)があります。教師期待効果とも言われるピグマリオン効果は、「他者から期待を受けることで、学習や仕事などで期待に沿う成果を出すことができる効果」のことを指します。ポジティブな期待を受ければプラスの成果を、ネガティブな期待を受ければ良くない成果を被教育者が生みやすい、と言われています。
一見ポジティブ・ハロー効果に似ていますが、ハロー効果が「評価時の評価者の認知のクセ(バイアス)」を説明しているのに対し、ピグマリオン効果は、「育成者の心得」といったニュアンスが強く、ハロー効果とは異なる考え方と言えます。
採用・面接におけるハロー効果6例
以下では採用の現場でよく見られるハロー効果の6例をご紹介します。注意したい事項として参考にしてください。 1.学歴
有名大学や海外の大学出身である事実を、その人全体の評価に直結させてしまうのがこのケースです。もちろん高学歴であることは、それに至る努力や実行力をポジティブに評価することができますが、その人物固有のスキルや企業とのマッチ度が学歴で保証されるとは限りません。学歴は尊重しつつも、それ以外の要素も丁寧に見極めることが求められます。
2.前職での役職
役職名などの肩書も、ハロー効果を生む要素として有名です。CxO、マネージャー、部長、課長といった肩書を職務経歴書で見た瞬間、「偉い」という認識が「スキルがある」「成果を出す」といった見解に繋がるケースがこれです。
前職での成果創出が高い職位に繋がったと考えることは間違いで�はありませんが、会社の規模の違いや求められるスキルの違いが大きいことを忘れてはいけません。たとえば、WEB系ベンチャー企業のCTO(最高技術責任者)が、必ずしも大企業の大規模システムを統括できるエンジニアスキルを持つかと言えばそうではありません。冷静に、スキルマッチの観点から人物評価を下すべきでしょう。
3.スキルの拡大解釈(語学力・資格)
英語が堪能、難関資格を保有している、などの要素もハロー効果に繋がる可能性があります。もちろん、募集要件として語学力や特定の資格を求めている場合はそれを確認すべきですが、必ずしも「英語ができること=グローバルな仕事ができる」ではありません。1つの特徴として評価しつつも、その他の重要な評価事項もフラットに見極めるべきでしょう。
4.容姿
意外と大きな影響を与えるのが、容姿のハロー効果です。人間の主観の怖さが出るところではありますが、「清潔な印象」「顔立ちが整っている」「健康的な体型である」といった第一印象が、採用の前半から終盤まで影響を持つ可能性が指摘されています。
容姿は人物固有の性質であり、それを持って判断されるべきではありません。この反差別の考え方に基づいて、例えばアメリカでは履歴書に顔写真を貼ること自体が規制されていますし、Anti-discrimination Law(反差別法)などの法律で、年齢や性別、結婚(離婚歴)、子どもの有無、家族構成といった個人情報も採用判��断で使用してはいけないと定められています。
採用の現場では、意識的に容姿を判断軸にすることはもちろん、無意識に採用候補者の見た目が採用判断に影響している可能性に留意することが重要でしょう。
5.外向性
「元気な挨拶ができる」「印象が明るい」「話すのが上手」といったいわゆる外交的な振る舞いができる人材は、面接においてポジティブな評価を得やすい傾向があります。営業職などの採用では、外向性は仕事力に直結するケースがありますが、これは全ての職種にあてはまるわけではありません。「明るくて話しやすい印象が、実力を大きく見せる要因になっていないか」と慎重に判断すべきでしょう。
6.面接官との共通点
面接官と同じ大学の出身であったり、同郷であるとわかった途端、その人物に対する評価が向上してしまうケースがあり、これもハロー効果で説明できます。言うまでもなく、出身大学や郷里は、仕事の実力と関係がなく、その好印象が面接に影響することは良いとは言えません。もちろん面接官も人間ですので、自分の感情に嘘はつけませんが、その感情を客観化する組織的な仕組みが必要です。
採用時のハロー効果への対策
ハロー効果が引き起こす評価エラーにはどのように対処すべきでしょうか。採用の現場で有効な対策を紹介します。 ハロー効果を組織的に理解する
まず重要なのは、「ハロー効果のような認知バイアスは発生しうる」と組織的に理解し、面接担当者に対して周知・教育することです。必ず主観は入り込むので、その前提で採用候補者を見極めるのだ、という共通認識を持つことが重要でしょう。
評価基準の明確化
面接官や採用担当者の主観を排除するために、採用要件を明確化し、要件に沿った人材か否かを評価できる質問を、組織的に作成しておくという対策があります。例えば、Googleが採用していることで有名な「構造化面接」は、この考え方に基づいた手法であり、参考になります。以下のコラムで詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。▼関連記事「構造化面接」に関する詳しい記事はこちら
構造化面接とは? メリット・デメリットや質問の作成方法をご紹介 複数の観点から見極める
採用候補者を見極める担当者の数をできるだけ多くする。性格テストや実践的なスキルテストを実施する。など、多角的に候補者を評価できる採用の仕組みを構築することもハロー効果のネガティブな側面を排除することに有効です。
リファレンスチェックで客観的な情報を得る
リファレンスチェックとは、採用選考の一環として採用候補者の現職(前職)の上司や部下、取引先などに、本人の仕事ぶりやスキル、人柄などについてヒアリングすることです。候補者が自己申告する書類や、面接官の主観を排除した、客観的な情報を取得できることが特徴で、欧米ではすでに95%以上の企業が導入する一般的な採用手法です。リファレンスチェックでは推薦者(候補者についての情報を提供する回答者)を複数人設定する場合が多く、多面的な情報を得られる点でも優れていますし、何よりそれらの情報が「実際に候補者と関わった人間の生の声」である点が特徴的です。面接で感じた印象や履歴書上の目立つ要素とは別の側面が見つかるケースが多くあります。▼関連記事「リファレンスチェック」に関する詳しい記事はこちら
リファレンスチェック実施企業の声。なぜ導入? 実施状況調査も解説リファレンスチェックにかかる費用は? 料金相場&費用に違いを生むサービス内容を解説! リファレンスチェックならエン・ジャパンの『ASHIATO(アシアト)』
エン・ジャパンが提供するリファレンスチェックサービスの「ASHIATO」は、オンライン完結型で手軽にリファレンスチェックを導入することができます。企業側の事前準備は約5分で完了、推薦者からは平均3営業日以内に回答を返していただけるというスピーディな運用の中で、採用の見極め精度向上に寄与します。また、推薦者から得られた情報から候補者の傾向を予測し、面接時にチェックすべきポイントや質問例をレポートする『面接官アドバイス』機能もあります。さらにエン・ジャパンの30年にわたる適性検査の開発・運用ノウハウと115万人以上の受検データをもとに開発した、推薦者からの『他己分析テスト』の結果がレポート提供されるなど、採用大手エン・ジャパンならではの機能も充実しています。2020年10月のサービス開始依頼、多様な業種で導入いただいており、導入社数が4,500社を突破したASHIATO。ご興味ある担当者様はまずフォームからお問い合わせください。▼関連記事・構造化面接とは? メリット・デメリットや質問の作成方法をご紹介・ミスマッチとは? アンマッチとの違いや原因、対策を解説・履歴書に嘘を書くと犯罪? 嘘を書いてはいけない理由と、発覚時の対応方法