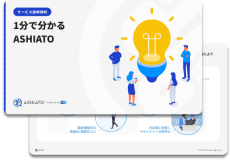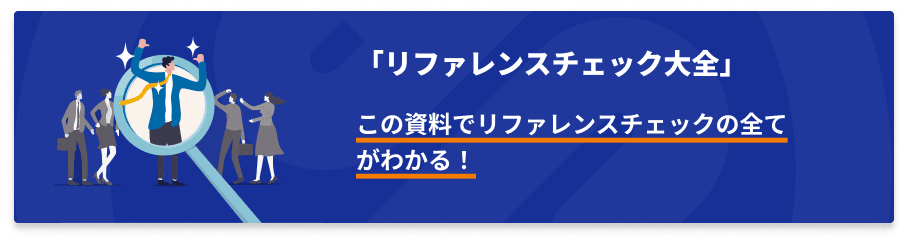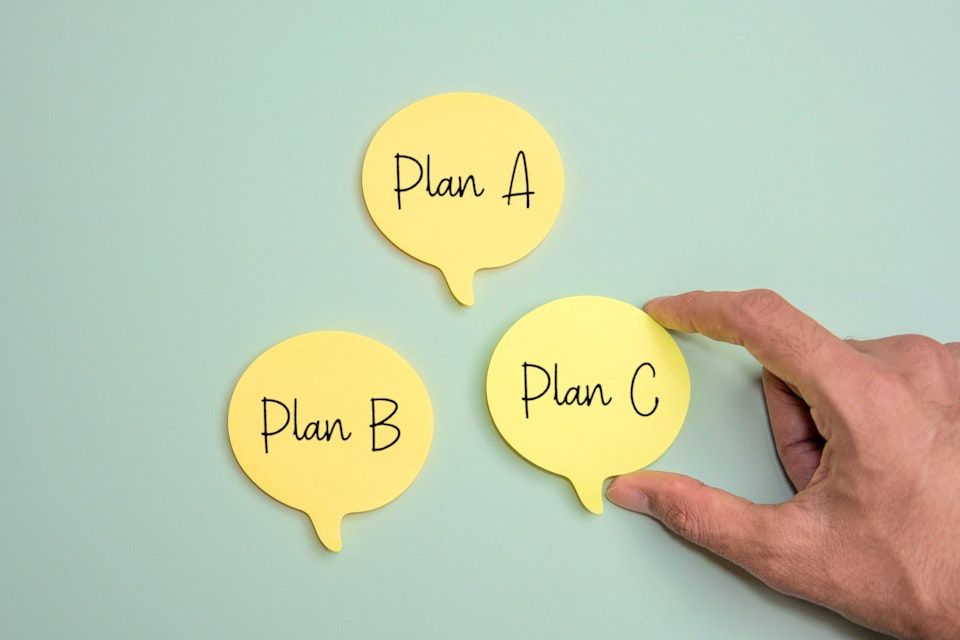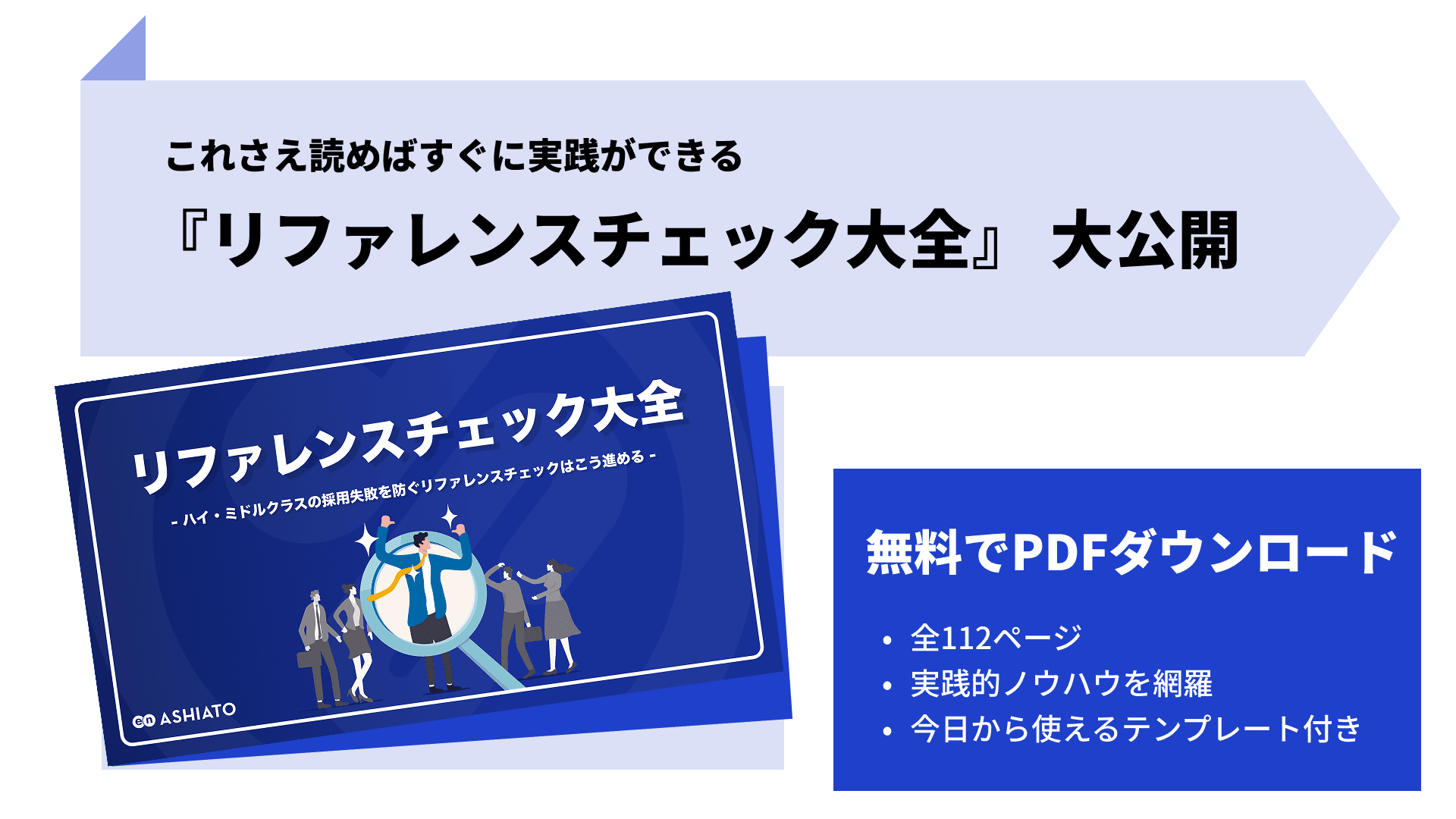「中途採用の候補者が優秀かどうか、もっと客観的な材料が欲しい。でも、現職の上司や同僚にリファレンスを依頼するのはさすがに無理じゃないか?」そんなお悩みを抱える採用担当・人事の方は意外に多いのではないでしょうか。近年、リファレンスチェックを導入する企業が増えつつあります。ところが、候補者が在職中の場合は転職活動を現職企業に知られたくないため、「現職への照会は絶対に避けたい」という声が多く挙がっています。企業側としても、無理に依頼した結果、候補者からの信頼を損ねたり選考辞退されてしまったりするリスクは避けたいところでしょう。そこで本記事では、なぜ��現職にリファレンスチェックを依頼することが難しいのかを詳しく解説しつつ、代替案や候補者への配慮方法をスマートにご紹介します。“現職に頼めない”ときでも有効にリファレンスチェックを活用するヒントをつかんでください。
【無料ダウンロード】
リファレンスチェックの全てを網羅的に解説をした資料も併せて確認いただくと、より具体的なイメージが持てる内容となっています。
エン・ジャパンのリファレンスチェック
ASHIATO(アシアト)は、採用を支援するエン・ジャパンが運営する、オンライン完結型のリファレンスチェックサービスです。採用候補者と一緒に働いた経験のある��第三者から、採用候補者の人柄や実績といった「働いてみないとわからない情報」を取得できます。詳細を知りたい方はぜひご覧ください。
その他リファレンスチェックに関するお役立ち資料はこちら。
現職にリファレンスチェックを依頼できない理由とは?
まず、一般的に現職へのリファレンスチェックが難しい背景についてご説明いたします。
候補者が転職活動を現職に知られたくない
在職中に転職活動をしている候補者は、現在の会社にバレることを極度に嫌がります。これが発覚すると、評価が下がったり、場合によっては居づらくなってしまうリスクがあるからです。
「リファレンスチェック=現職に問い合わせ」と受け取られてしまうと、多くの候補者は強い不安を覚え、最悪の場合選考辞退を検討することもあります。
POINT
・候補者側にとって、在職中の転職活動は“外部に知られたくない”センシティブな問題。
・無理な照会要求は、最終面接前でも辞退につながるリスク大。
個人情報保護法��などの法的リスク
日本の個人情報保護法では、本人の同意なく個人データを第三者から取得することが厳しく制限されています。
候補者が明確に「現職への照会はNG」と言っているのに強行すれば、違法性を問われかねません。さらに、同意を事実上強制すると、「強要罪」に問われる可能性も指摘されています。
現職側にも協力する動機が薄い
「退職してほしくない」「忙しくて余裕がない」「社外の採用プロセスに関わるのは抵抗がある」といった理由で、現職上司や同僚が協力を拒むケースも多く見られます。仮に候補者がお願いできたとしても、快く情報提供してくれるとは限りません。
評価が偏りやすい
仮に現職からリファレンスが取れたとしても、上司や同僚との人間関係が悪かったり、上司が優秀な部下を手放したくなくて過度にマイナス評価をする、といったケースも考えられます。「現職の評価=客観的情報」ではない可能性が大いにあるのです。そのため企業側にとっても、現職リファレンスだけに依存する採用判断はリスクが高いと言えます。こうした背景から、「現職にリファレンスチェックを依頼するのは難しいし避けるべき」という認識が、国内外問わず一般的です。次の章では、具体的に現職への依頼がもたらすリスクをさらに深掘りしていきましょう。
現職に依頼すると招くリスク:候補者辞退から法的問題まで
現職へのリファレンスチェックを強引に進めようとすると、どのようなリスクが潜んでいるのか。以下の表にまとめてみました。
候補者が選考辞退・離脱するリスク
リファレンスチェックを求められた瞬間、候補者が真っ先に考えるのは「現職にバレるかも」という不安です。実際、「絶対無理」として辞退されるパターンも珍しくありません
専門家の声 「在職中に転職をしている方ほど、現職バレは大きなリスク。ここを軽視すると、有望な候補者をみすみす取り逃がすことになります。」 (エン・ジャパン株式会社 小野山 伸和)
候補者との信頼関係の毀損
最終選考間際まで良好だった関係が、「現職にも連絡を…」と言った途端に急速に冷え込むケースもあります。
一部では、「選考途中でリファレンスの同意書を取り付けようとしたら、候補者が“現職に絶対知られたくないので辞退します”と即答した」という事例も。企業イメージに悪影響を及ぼすリスクが非常に高い行為です。
法的リスクと社会的信用の失墜
個人情報保護法に基づき、候補者の同意なしに現職へ問い合わせるのは違法性があるとされています。
また、同意を求める際に事実上の強制となれば「強要罪」に問われる可能性も。現職照会によるトラブルで訴訟に発展すれば、企業のコンプライアンス違反として広く知れ渡ってしまい、イメージダウンは避けられません。
採用判断ミスのリスク
仮に現職上司から「この人は仕事が遅い」とネガティブ評価を受け取ったとしても、それが個人的な確執や引き留め策略によるものだったらどうでしょう? 不正確な情報を鵜呑みにして、せっかくの優秀人材を落としてしまう可能性があります。企業としても現職リファレンスだけに頼るのはリスクが大きいといえます。
「無理」の場合を考えるリファレンスチェックの代替策5選
「現職から取れないなら意味がないのでは?」と思うかもしれませんが、リファレンスチェックの本来の目的は「候補者の人柄や仕事ぶりを客観的に知ること」です。
現職が難しくても、その他の手段を組み合わせることで十分に有益な情報が得られます。ここではおすすめの代替策を5つご紹介します。
前職・前々職の上司や同僚に依頼する
・直近ではなくても、実務で一緒に働いた人からの評価は貴重
・候補者にとっても協力を依頼しやすく、転職活動がバレるリスクを抑えられる
・「上司との関係が悪くて前職を辞めた」というケースでも、他の部署の同僚や先輩を推薦者にできればOK
現職でも既に退職している元上司・元同僚に依頼
・現職企業の社員でも、既に退職した人ならバレるリスクが低い
・現在と比較的近い時期に同僚だった場合、情報の鮮度もそれほど落ちない
・候補者が「退職者であれば協力してくれそう」という相手をピックアップするケースも増えている
上司以外(同僚、取引先、部下など)の推薦者を検討
・リファレンス=上司からの評価だけに限定しない
・取引先や他部署メンバーのほうが、日常的に仕事ぶりをよく見ていることもある
・管理職候補なら部下やチームメンバーからの信頼度など、上司視点とは違う評価が得られる
タイミングを工夫する(退職後や内定後に実施)
・最終選考~内定提示のタイミングで候補者に同意を得る
・どうしても現職から情報が欲しい場合、退職の承諾が出た後に連絡する方法も
・ただし日本では内定後の取り消しが原則的に困難なので、あらかじめ企業法務と連携してリスクを検討
他の評価手法を活用する(ワークサンプルテスト・適性検査など)
・リファレンスチェック以外にも、候補者の能力を多角的に測る方法は多数存在
・ワークサンプルテスト(実務テスト)や適性検査などで客観的にスキル・特性を把握
・「リファレンスに頼らずに人材を評価する」という選択肢を組み合わせることで、現職に照会しなくても十分��にミスマッチを防げる
参考情報 エン・ジャパンが提供するツールやアセスメントの活用事例を見ると、ワークサンプルテスト導入で採用精度が高まったケースが多く報告されています。リファレンスチェックだけでなく複数の評価軸を持つことで、不確定要素を減らすメリットがあるのです。
候補者の信頼を守るコミュニケーション術
リファレンスチェックをスムーズに進めるためには、候補者への配慮ある伝え方が欠かせません。ここでは実務で使える具体的なフレーズやメール例文を紹介します。
事前説明と同意の取り方
・できるだけ早い段階で「リファレンスチェックを行う可能性があります」とアナウンス
・「現職には一切連絡しませんのでご安心ください」としっかり明言すると不安を軽減
・��候補者が同意してくれた場合も、「本当に大丈夫か?」と再確認する配慮を
(例)候補者への連絡メール文面
件名:リファレンスチェック実施に関するご相談(◯◯様)
◯◯様
いつもお世話になっております。△△株式会社 人事部の□□です。
この度は当社の採用選考にご応募いただき、誠にありがとうございます。
最終選考にあたり、◯◯様のこれまでのご活躍をより客観的に把握するため、
「リファレンスチェック」を実施させていただきたく存じます。
なお、現在ご勤務中の企業様へは連絡いたしませんのでご安心ください。
ご協力いただける前職の上司・同僚の方などがおりましたら、
お差し支えのない範囲でご紹介をお願いできれば幸いです。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
△△株式会社 人事部
□□(署名)
...
・ポイントは「現職へは一切連絡しない」ことを繰り返し伝えること。
・候補者のメリット(ミスマッチ回避、適切な評価につなげる)にも触れると、協力を得やすくなります。
推薦者の選定を候補者と相談
「前職のどなたが一番候補者様の働きぶりをよく知っていらっしゃいますか?」と質問し、候補者自身に安心な相手をリストアップしてもらうのがスムーズです。無理をさせずに、「最終的に推薦者を決めるのは候補者本人」というスタンスを崩さないようにしましょう。
推薦者へのコンタクトメール・電話例
推薦者へ連絡をする際は、件名や本文で「××さん(候補者)からご紹介いただいております」と明示し、守秘義務も約束します。
(例)推薦者への依頼メール(抜粋)
件名:リファレンスチェックご協力のお願い(◯◯様推薦者:△△様)
△△様
はじめまして。△△株式会社 人事部の□□と申します。
◯◯様(候補者)より、貴殿のお名前をご推薦いただき、
過去のご勤務ぶりやお人柄についてお話を伺いたくご連絡しております。
<リファレンスチェック概要>
・目的:選考候補者の実務能力・人柄を客観的に理解するため
・回答方法:お電話またはアンケートフォーム
・所要時間:約15分~20分
・守秘義務:回答内容は当社以外の目的には使用いたしません
ご多用のところ恐縮ですが、可能な範囲で率直なご意見をい��ただければ幸いです。
...
・「回答は選考以外の目的で使用しない」と明言し、安心してもらうのがコツ。
実施後のフォロー
リファレンスチェックを完了したら、候補者に一言お礼を伝えると好印象です。詳しい内容までは開示できない場合でも、「ご協力ありがとうございました。現在、最終審査を進めております」と進捗を共有すると安心感を与えられます。
海外と日本でのリファレンスチェックの違い
実は、海外でも「現職に直接連絡する」というやり方はほとんど行われていません。アメリカや欧州の多くの企業では、候補者があらかじめ数名の“リファレンス(推薦者)”をピックアップし、その範囲内で問い合わせるのが一般的だからです。
応募フォームに「Can we contact your current employer?(現職に連絡してもよいか)」という欄が設けられている場合でも、Noを選択すればそれ以上は強要されないのが通常の運用です。
一方、日本では長らくリファレンスチェック文化が根付いておらず、「前職証明書の確認」程度がせいぜいでした。
しかし近年、経歴詐称や採用ミスマッチを防ぐために注目されるようになった背景があります。制度としてまだ新しいため、候補者の理解や法的整備も十分でないのが現状です。だからこそ、「日本の候補者にどう説明するか」「現職照会は避けるべきか」という点で戸惑う企業担当者が多いのです。
海外事例のポイント
・現職に“無断”で照会するのは非常識と捉えられる
・候補者が自分で用意するリファレンスリストから確認するのがスタンダード
・日本国内でも外資系企業の採用では同様の手法が多く、「現職企業は除外」して確認するのが通例
まとめ:現職NGでもリファレンスチェックは工夫次第
「現職には絶対依頼できない=リファレンスチェックが無理」ではありません。
むしろ現職依頼には法的・実務的に大きなリスクがある以上、前職・他の推薦者から客観的な情報を得る方法をメインに検討するのがベストです。
候補者へのコミュニケーションも丁寧に行い、配慮ある進め方をすれば、リファレンスチェック本来のメリット(採用ミスマッチ防止・客観的な評価材料)を享受できます。
ポイント再確認
・候補者に現職照会を求めるのはリスク大
・前職・元上司・取引先など代替手段は多彩
・候補者への伝え方(メールテンプレ、説明時期)次第で信頼関係を維持
・海外でも「現職に無断で連絡」は非常識。日本も同様に注意が必要
優秀な人材を逃がさないためにも、リファレンスチェックを上手に活用する工夫が求められます。 もし進め方や実施フローに不安がある場合は、法的知識やアセスメント手法に明るい専門家やサービスを活用するのも有効です。ASHIATOでは、カスタマーサクセス担当含め、リファレンスチェックをきちんとサポートする環境も整っています。
エン・ジャパンの「リファレンスチェック大全」を無料ダウンロード!
本記事を監修するエン・ジャパン株式会社の小野山 伸和は、数多くのリファレンスチェック導入支援の実績を持ち、国内企業ならではの注意点や最新事例に精通しています。エン・ジャパンが提供する『リファレンスチェック大全』では、さらに詳しい実施ステップや法的チェックリスト、候補者への伝え方テンプレートを無料でご覧いただけます。- リファレンスチェックを行う上での具体的な手順- 候補者・推薦者へのメール文面や会話例- 個人情報保護対応のポイント- ミスマッチを最小化するチェックリストぜひ以下のリンクからダウンロードのうえ、貴社の採用活動にお役立てください。